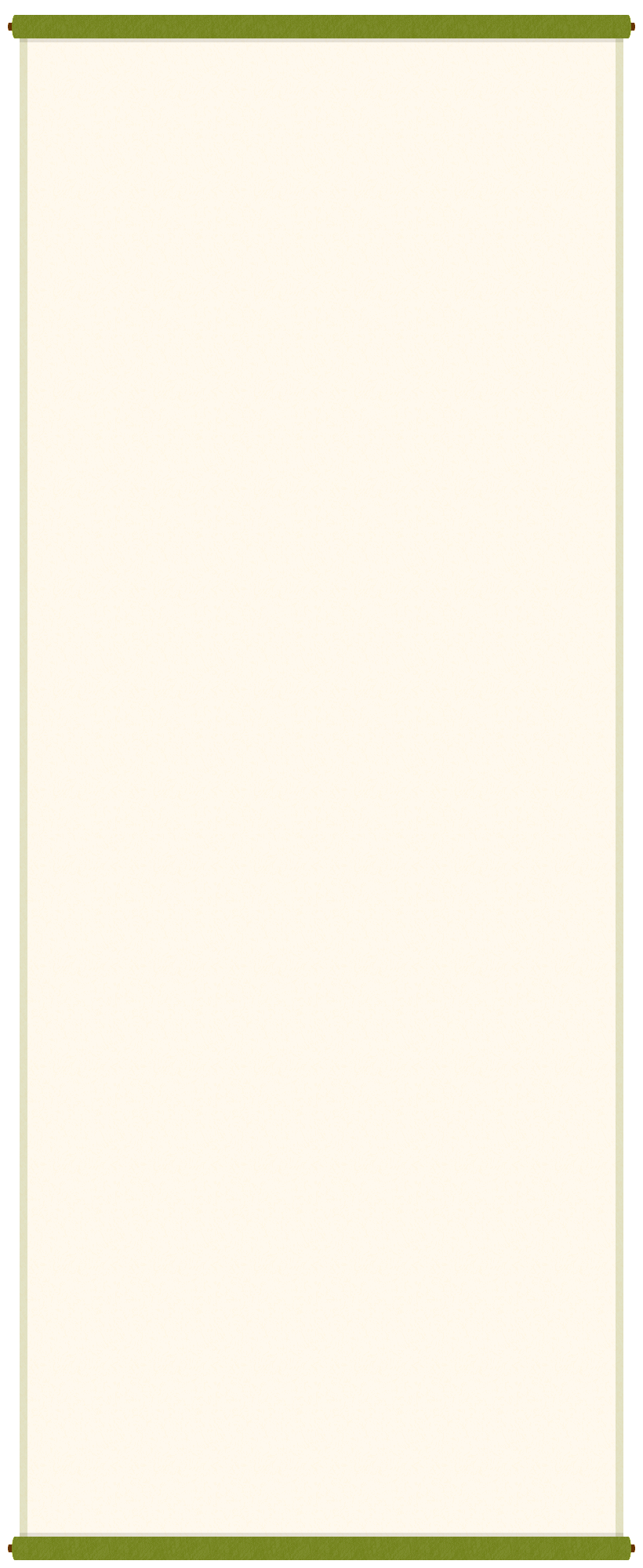

日本の侠客、最後の人

●新門辰五郎(しんもんたつごろう)
明治2年12月。どんよりと暗い雲間からもれる陽光に、巴川の水面が冷めたく光っている。浜通りと呼ばれる岸辺の狭い路には廻船問屋が軒を連ね、石垣づくりの船着場に、帆柱だけを寒風に立てた船が並んでいる。
上町から美濃輪に至る巴川沿いの清水八ヶ町には、徳川家康から駿河小早の称号をもらった誇り高き清水港の船問屋が明治維新ころまで30軒余も散在した。中でも甲州廻米置場対岸の本町、袋町あたりには播磨屋、三保屋、天野屋といった大店が密集していた。
吐く息から湯気が立つこの朝、本町の廻船問屋、松本屋の店先で、小僧の七蔵は普段よりも念入りに玄関の格子戸を雑巾で磨いた。彼がいつもより掃除に精を出したのはこの日、静岡から新門辰五郎という偉い親分が来て、次郎長親分と会うと、主人平右衛門から言われていたからである。
次郎長の住む上町は、目と鼻の先だ。昼近くなると口をへの字に結んだ次郎長が、幅広い肩を揺すりながら現れ、平右衛門の案内で奥座敷に通る。
ほどなく、一台の人力車が松本屋の玄関先に着き、白髪長身の老人が降り立った。江戸町火消「を組」の頭領、新門辰五郎である。顔の色つやは70歳とは思えない。次郎長はこの時、50歳だ。
「何かむずかしいことが始まるのかもしれない」と七蔵は思いながら、主人に命ぜられて用意した白木の三宝に銚子と盃を乗せて、薄暗い奥の間に運ぶ。十畳の座には、主人の平右衛門をはさんで、次郎長と新門辰五郎が向かい合って座っていた。
両雄の会見の様子は、明治2年のこの時から60年以上もたった昭和のはじめ、保田七蔵によって語り明かされた。函館に渡って成功した七蔵少年は、余生を送るため、生まれ故郷の清水に帰っていたのである。次郎長、新門辰五郎両雄の会見は、いったいなんだったのだろうか。
辰五郎はこのころ、静岡常光寺に居住していた。徳川慶喜の護衛役を自任する辰五郎は、将軍の座をおりた慶喜に影形のように寄り添い、水戸からもはるばる随行して、主人が謹慎のため入った宝台院近くに住んでいた。
謹慎が解け、紺屋町の大官屋敷跡に移った慶喜は連日のように清水港に通い、投網や釣りなどに無聊を慰めた。人力車のお供はわずか一人である。
辰五郎が次郎長に会ったのは、徳川びいきの地元とはいえ、いかにも無防備な元将軍の身辺を「守っていただきたい」と実力者に託すためだったのである。自らの役割を終えたとみたかのように、辰五郎は明治4年、東京に引き上げる。
幕臣であり、教育家、江原素六は次郎長、新門辰五郎の二人をよく知っていたが、「共にあくまで男らしくて、胆(きも)が恐ろしく大きい。恐らく、彼らは日本の侠客というものの打止めであろう」と評した。(「日本及び日本人」)
辰五郎は若い時、大名火消の中でも横暴な有馬火消に憤激し、部下を率いて闘い18人を殺し、町奉行所に自首した。町奉行は辰五郎の方にも理があるとして、死罪になるところを江戸払いとなったが、後に浅草に復帰した。辰五郎の侠客としての名声があがったのはそれ以来である。
明治8年、75歳で波乱の生涯を閉じる。
「思いおく鮪のさしみ、ふくと汗、ふっくりぼぼに、どぶろくの味」が辞世の句。
産経新聞 平成11年(1992年)2月10日 水曜日 『文化』より