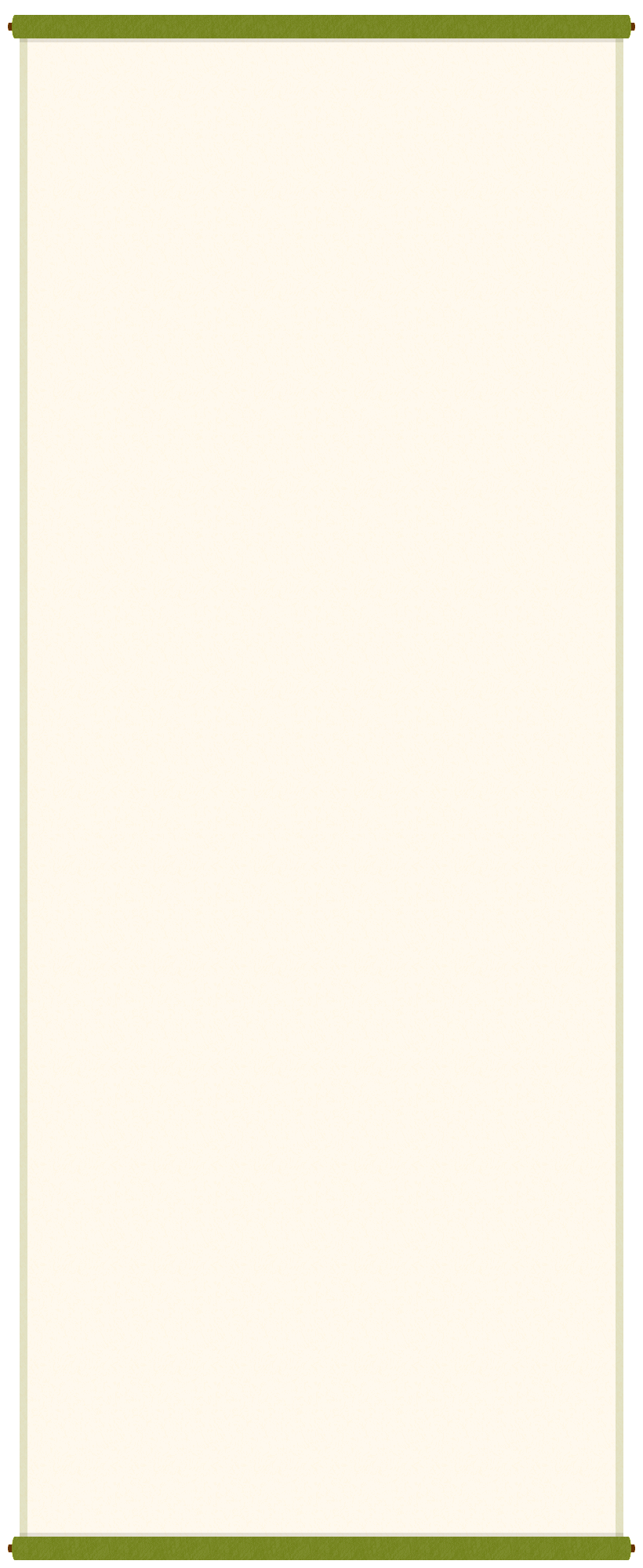

「廃仏」の流れに逆らい仏門に
月3銭募金で本堂再建

●万休和尚(ばんきゅうおしょう)
明治19年、まだ石堤も新しい清水港の船着場に、横浜からの第2福沢丸が着き、2日がかりの船旅を終えた乗客たちが、ぞろぞろと上陸した。
その中に頭を丸めた2人の僧が―1人はまだ年端も行かぬ子供だったが、荷物をかかえて歩いていた。一見してどこそこの寺の住職とその小僧弟子といった体の2人は、船着場の目の前にある船宿に入って行く。
羽目板も屋根瓦も真新しい二階建の船宿は、開業したばかりの「末廣」である。 末廣に投宿した2人の僧の1人は、青梅(東京都)の玉泉寺住職から不二見村下清水(清水市)梅蔭寺に転任する万休宜哲(ぎてつ)和尚、1人は弟子の宜雄(ぎゆう)である。
末廣は、いうまでもなく晩年の次郎長が3代目お蝶さんに切り盛りさせて経営した船宿である。横浜からはるばる船に乗って、ここに一夜の宿をとった2人は、この日から清水次郎長と切っても切れない深い関わりを持つようになった。
次郎長一家にフグを食わせたことで知られる宏田和尚の後継、梅蔭寺14世住職となった万休和尚は、後に次郎長の葬儀を営み、戒名の「碩量軒雄山義海居士」を付けた人でもある。 万休和尚が梅蔭寺に赴任した当時、寺の本堂は安政の大地震で倒潰した後、仮に建てられた粗末な建物だった。
住職の万休はこの本堂再建を思い立ち、檀信徒に呼びかけ「月掛3銭」の募金を計画して、まず世話人の有力者である次郎長に相談した。 相談を持ちかけられた次郎長は、自分の息子ぐらいの年ごろの万休和尚の顔をまじまじと身ながらこう言った。 「キミは紀州から来たご用木だ。お前のような男なら必ずやれる」 紀州から来たご用木とは、万休和尚の出身が紀州(和歌山県)であり、真面目一方の堅物であることをいうらしい。
ちなみに万休和尚が梅蔭寺に入ったときは34歳、次郎長は66歳である。次郎長が見抜いた通り、万休和尚はコツコツと「月3銭」の掛け金を集め、20年近い歳月をかけて立派な本堂を再建した。 万休和尚の姓は金谷、名は宜哲、嘉永5年(1852)和歌山県田辺市近在の朝来(あそう)村に生まれ、同村の臨済宗妙心寺派円鏡寺住職革源和尚のもとで得度修行した。
私は10年ほど前、調べのため円鏡寺を訪ねたが、小高い境内から遥かに熊野古道の山なみが見えたのを印象深く覚えている。当時、田辺市立図書館の杉中浩一郎館長から万休和尚のルーツに関する資料について種々ご教示いただいたが、その中でここに記しておかねばならないことが2つある。
1つは、万休宜哲の兄弟子熊嶽(ゆうがく)宜黙のことである。熊嶽和尚は伊深(岐阜県)正眼寺の管長となった名僧だが、万休和尚より4歳年上の先輩。田辺市の酒店につとめ、明治元年21歳のとき、頭を剃り、円鏡寺革源和尚の弟子となった。万休和尚の位牌に記されている経歴に「田辺市の造酒家」とあり、兄弟子熊嶽と同時に仏門に入ったとみられる。廃物毀釈によって仏教が未曾有の危機を迎えようとする時期だ。
もう1つは、梅蔭寺の境内のミカン畑の中に「アンドウ蜜柑」という種があったが、そのルーツは、田辺藩の家老安藤家にあったという事実だ。植樹に熱心だった万休が、故郷から苗木を取り寄せて栽培したと思われる。 明治26年、次郎長が亡くなった年の秋、天田愚庵はその供養のため西国33箇所巡礼の旅に出るが、その途次、朝来の円鏡寺に熊嶽和尚を訪ねている。愚庵と熊嶽を結びつける接点となったのは万休和尚だ。 次郎長の予言通り、「月掛け三銭」で建てられた梅蔭寺本堂は、戦時中の大地震や空襲の被害も奇跡的にまぬかれ、間もなく棟上げから100年を迎えようとしている。
産経新聞 平成11年 5月26日 『文化』より